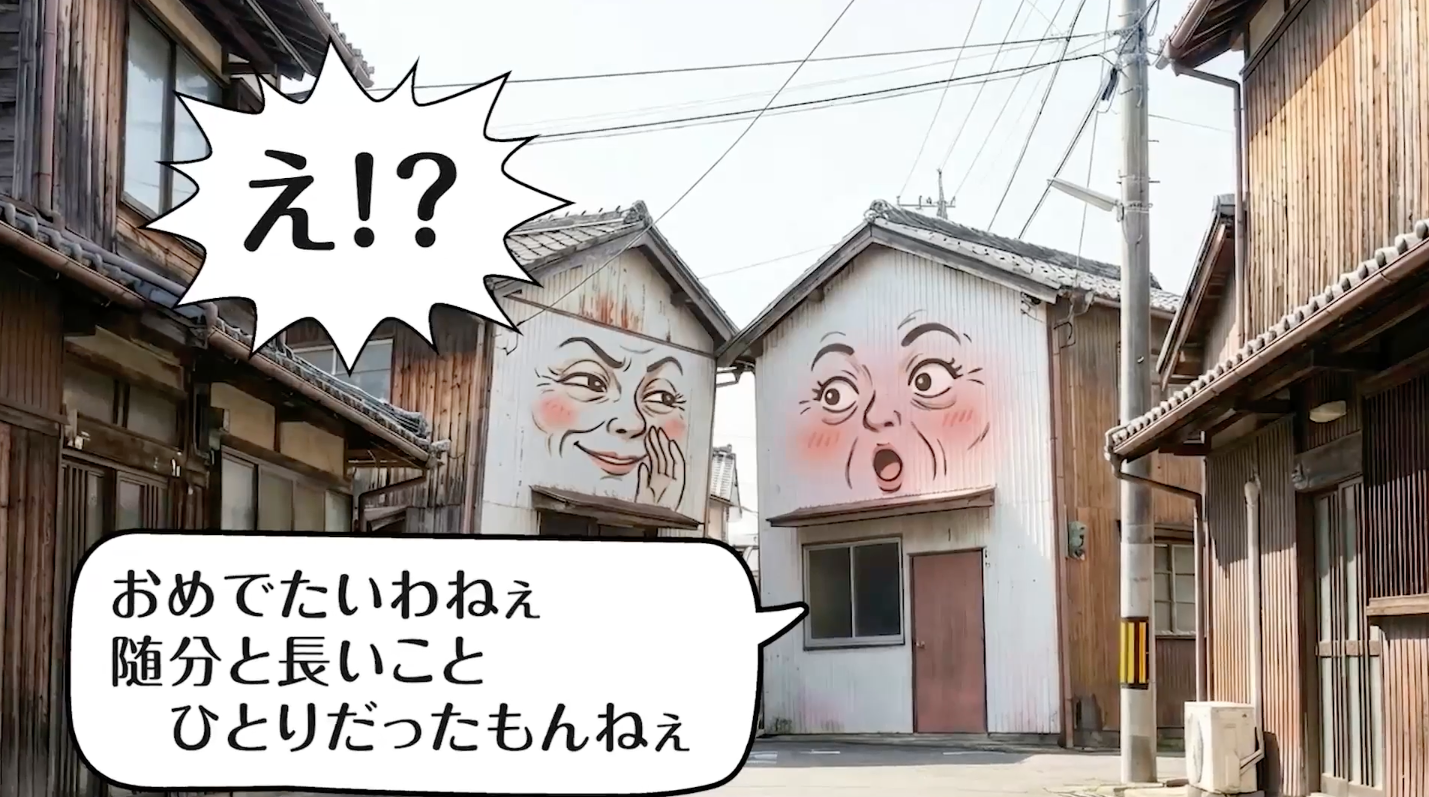“予算”という切り口から、漁業を考える
先日、財務省で水産庁の予算を所管されている方と、福田が「漁業」や「地域活性」について意見交換する機会をいただきました。
現場で感じていることや、脳動ゼミの魚脳講師陣から出た「合意形成を担う調整人材に予算を」という声をお伝え。後日、東京海洋大学の松井准教授からも「ぜひ話す場を設けて」と要望があり、2回目の機会をつくる流れに。
当日は、丘漁師組合として、水谷と太田に加え、漁師・大学・物流・林業など、分野の異なるメンバーとともに財務省へ。
・持続的な漁業につながるか?
・漁業従事者のリアルな課題とは?
・観点は「水産」か「地方創生」か?
それぞれの立場から問いを持ち寄り、「予算」という切り口で対話することで、現場・制度・ルール・情報の流れといった複数のレイヤーを具体的に往復できました。(財務省の方々が、現場の声に本気で耳を傾けようとされる姿勢にも感動)

・「海の話というより、日本全体の話」
・「漁村の廃業や廃棄の課題を初めて知った」
・「山と海に、同じ構造があると気づいた」
・「現場としても、既存ルールを見直す時期に来ている」
・「魚は身近だけど、経済合理性によって距離が生まれているなら、それを手繰り寄せる必要がある」
そんな声も上がりました。
我々は水産業界の人間ではありませんが、漁業や漁師の文化・哲学に惹かれた一人として、「あらためて自分たちに何ができるだろう」と視野を広げる機会にもなりました。
そして、三重県では、太田が行政時代に温めてきた一次産業・大学・行政・民間が連携する“コンソーシアム”が10年以上前から存在しており、分野を超えて語り合う土壌があります。
「50年後、100年後の地域の未来を、みんなで描けたら」
そんな言葉が自然と交わされる場に、“らしさ”を感じました。
これからも、“わからないこと”をわからないままにせず、生産地と消費地、主観と客観、解釈と事実を行ったり来たりしながら、必要な対話の場をつくっていけたらいいな。